
ベビーシッターに子どもを預けて海外旅行
いきなり何?
というタイトル
話せば長くなるのですが
さかのぼること約半年ほど前、仕事の研修で大阪に行ったときにアメリカから日本に来て間もないALTと話す機会がありました。当時末っ子は保育園の年長だったのですが、
『夕方や夜仕事があったり外出するとき、子供の食事やお世話はどうしているの?』
と質問され、週2日から3日は私の母(娘にとってはおばあちゃん)のところでご飯を食べさせてもらって待っていることを説明すると
『その時はお母さんにお礼としていくら払うの?
日本ってベビーシッターに預けるって感覚はないの?』
と結構前のめりにいろんな質問を投げかけられ、
ああ、ここにもあった。日本人とアメリカ人の感覚の違い…
と感じたのでした。
文化や習慣の違いなので、熱弁したところで理解はされないのですが
一度話し始めてしまった以上、途中でやめられず英語で一生懸命に言い訳(?)を。
はた、と考えたのですが
私の実母は自宅から徒歩10分。
子どもたちの通学路途中に住んでいるのですが
私にしても、子供たちにしてもおばあちゃんの家に寄ることや
私が仕事の時にはおばあちゃんの家でご飯を食べてお風呂に入ることが
日常的過ぎて感覚が麻痺…
もちろん日本人でも親と離れ転勤や引っ越しで親戚を頼れない人はたくさんいるので
母の近くに住んでいろんなサポートを受けられている私はとても幸せだと感謝しています。
ただ、彼女の意見としては
それは、一個人としての母の自由を奪う行為だと。
アメリカだとそういう時ベビーシッターにお願いしてお金を払って仕事として子どもの世話をしてもらうのが普通。
あーーーーそうなるか。
言っていることは理解できますけど…。
日本にはあまりお金を払って
いわばプロであるベビーシッターに子どもを見てもらうという習慣もないし
母がいないと私の生活は成り立たないぐらいおんぶに抱っこ依存しているのですが
子どもたちもおばあちゃんが大好き。
おばあちゃんも孫の成長を近くで見られて幸せ。
私自身も他人よりも、自分を育ててくれた信頼できる人(母)が子どもを見てくれる安心感。
誰も損してないやん😊
アメリカ人の彼女には最後まで理解されませんでしたが
でも
お金払うし、プロかもしれないけど(学生かもしれませんが)
ベビーシッターに子どもをあずけて1週間海外旅行に行く感覚。
逆にそっちのほうがないわ~
と思ったのでした。
というお話。
アメリカ人全員がそうとも思わないですし、
彼女の周りだけのことかもしれないですけどね。
まご、子との関わり方についてのお国柄まだまだあります(笑)

姫路市立美術館
チームラボ
世界は暗闇からはじまるがそれでもやさしくうつくしい
観に行ってきました。
触ると変化する映像にお子さんたちも興味津々。
幻想的な世界観
スクリーンの前でアクションを起こすと画像に変化が生まれる不思議。
国内外で愛され親しまれているデジタルアート
姫路で見られるなら是非!!
と観てきました。
あと数日ですが是非体感されてみてくださいね。
6/16日までの展示開催。
斬新な展示はさることながら
赤煉瓦の明治モダン建築の姫路市立美術館そのものの美しさに改めてはっとさせられました。
1900年代初頭に戦争中陸軍の倉庫、陸軍姫路兵器支廠・被服倉庫として建築され
戦後は姫路市役所として利用されていました。
美術館として開館したのは1983年。
意外と最近なんですね。
夜はほんのりライトアップされていてなんとも言えず荘厳で綺麗です。
姫路市民の灯台下暗しスポット。

意外なストレス対策
ストレスが多い現代人。
ストレスにもいろんな種類があると言われています。
大きく分けて以下の4つ。
①人間関係のストレス
子どもとの関係、夫婦間の関係、仕事上の人間関係をはじめ家庭内外で起こる精神的ストレス。失恋や解雇、子供や夫婦間の意見の衝突によるものも。
②物理的ストレス
寒い、暑い、気圧、騒音などが物理的に体に及ぼすストレス。
③科学的ストレス
酸素の欠乏や過剰、栄養不足、栄養過多、薬害などによるストレス。
④生物的ストレス
病気、怪我、不規則な生活、過労、睡眠不足などによるストレス。
生きているとみんな多かれ少なかれこの4種類のストレスを抱えているとされています。
ストレスを全くなくせばいいということでもなく、
適度なストレスは、よい緊張感となり心身、脳に良い刺激を与えて集中力を高めることもありますが、過度のストレスは血圧の上昇や自律神経の乱れなどにつながり、疲労が蓄積するうちに病気にかかりやすくなったりします。
まじめな人や、神経質な人、何でも我慢して内にため込んでしまう性格の人。
このようなストレスを感じやすい人もいるし
過酷な状況でも楽観的でネガティブな感情やストレスを引きずらない人もいますが、
どちらにせよ、ストレスはほどほどにうまく付き合っていく必要がありますね。
ここで、あるおもしろい研究報告。
アメリカのイェール大学の実験で2週間にわたって毎日のストレスレベルと、誰かに対して行った小さな親切を記録してもらったそうです。
実験の結果、小さな親切をした人ほど
①ポジティブな感情の量が多い
②メンタルヘルスの悪化が少ない
③ストレスに強い
という傾向がはっきり出たそう。
逆に親切が少ない人は
①ネガティブな感情にとらわれやすく
②メンタルヘルスが悪化しやすい
という傾向。
『親切』はする人もされる人もどちらにも利点がある。
という研究結果。
ストレスによってネガティブな感情に支配されないように、
だまされたと思って『小さな親切』を積み重ねてみるのもいいかもしれませんね。

Instagram ダイレクトメッセージサポート終了
当教室LAC英会話教室は Instagram Facebook のSNSを利用しているのですが、
昨日のニュース Instagram ダイレクトメッセージ機能が来月廃止になるという記事。
今までの会話履歴はそのままInstagramアプリに引き継がれるので特に操作は必要ないとのことですが…。
今年2019年1月、Facebook CEOのマーク・ザッカーバーグは、3つのSNS(Facebook、Instagram、Whatsapp)におけるメッセージアプリの統合、それぞれのアプリは個別で存続するものの、インフラを整備して1つに整えるという計画を発表しました。
InstagramのメッセージアプリDirect。FacebookのメッセージアプリMessengerはとても有名ですが、実は広く知られていないだけでFacebook傘下のアプリは他にも多数。たとえば、昨年11月にリリースされたTikTokに対抗するLasso。2018年12月にリリースされた子ども向けのメッセージアプリMessenger Kids。2017年秋に再リリースされたイベント系アプリFacebook Local, Workplace Chat. Instagramには編集アプリのLayout,Boomerang.
それぞれのSNSにはまだまだ関連するアプリが相当数あって、統合することによってそれぞれのサービスのユーザーの管理がしやすくなり、より多くのデータを集めることができる。そして、各サービスを紐づけておくと、規制や取り締まりがあったときに、会社を特定し分けにくくなるということから、Facebookに大きな利益があると考えられています。Facebookは膨大なユーザー情報を集めることでビジネスが成立していますが、その一方で常に物議を醸す会社であると言えますよね。多くのサービスを持つFacebookという企業を、足元をすくわれずより強固にするためには管理しやすいインフラが必要なのでしょうね。
という堅苦しい話をつらつらと書いたのですが私が今日言いたかったのはそんなことではなくて…それはとりあえず横に置いておいて…
Facebookが世に知られ始めて自分自身が使い始めた時、一番長くて15年は音信不通だった学生時代の友達とまたつながることができたケースがたくさんあります。
その時思ったのは
『マークザッカーバーグさん。あなたに感謝』
まさかまさか学生時代にはこんなスマホ一つであれこれできるなんて思っていないし、ましてや連絡がつかなくなってもしかしたら今生の別れとなっていたかもしれない友人と交流が再開するなんて思ってもみなかったです。
今回もInstagramのDirect機能の廃止がもう少し早ければ出会えてなかったかもしれない人がいる。
アプリ、ソフト
たくさんありすぎて使いこなせているのは本当にごく一部。
その数少ないたまたま利用していた機能がマッチしてまさに一期一会の出会いを生み出したんだなーと思うとちょっとしみじみしてしまったのでした。
大げさかもしれませんが。(笑)

Pinnacles Desert Lookout and drive.
私が今まで見た景色のうち、一生忘れられないであろう衝撃的な光景。
オーストラリアパースに留学中にホストファミリーに連れて行ってもらったピナクルズ。
パースから車で約3時間北上したところにあるナンバン国立公園内にあるこの砂漠の不毛地帯。
日本は島国なので水平線を見ることは簡単にできますが、生まれて初めて見た地平線に沈む太陽と遥か遠くの動物たちのかすかな影。
言葉では言い表せない感動が押し寄せてきた事を今でも鮮明に思い出せます。
大人になると日々生活することに一生懸命で、自分の外にある世界に目を向けづらくなる一方で、めいっぱい仕事したらめいっぱい休む。プライベートの充実を積極的にアクティブに過ごす。なかなか難しいのですが、そんなハリとつやのある生活を目指したいなと日々考えています。
大人はもちろん子どもたちにも生徒さんたちにもちゃんと息抜きの時間、心から楽しめる時間、つらいことがあったら充電する時間を持ってほしいなと思うのです。
そして日本では考えられない出来事、絶対に見られない景色、貴重な体験をどんどん積み重ねてほしいです。
先日娘が修学旅行で軍艦島に上陸しましたが、『ママ、軍艦島グーグルアースでみれるで!!』と自慢げに話してきました💦
テクノロジーの賜物グーグルアースで空から様々な場所を見ることはできますが、実際肉眼で、その場所の熱気、温度、においを感じることや五感を刺激することはできませんよね。そんな貴重な体験を多感な子どものうちに肌で触れて感じてほしいと心から思った瞬間でした。
ああ、海外旅行に行きたい。

話す言葉によって顔が変わる
これはよく知られていることなのですが、話す言語や話し方によって骨格が変わる。という事実。
ALTや塾の外国人講師と話していると、私はほかの日本人に比べて百面相なのだそうですが
(よく言うと表情豊か。悪く言うと喜怒哀楽がすぐ顔に出る。)
特に日本語は口を大きく開けなくても話せる言語なので、日本語にない”TH”の発音や縦や横に大きく口を開けて話す母音音などは早口で話そうとすると結構顔周りの筋肉をつかうのです。
確かにちゃんとネイティブの発音のトレーニングをしている人は日本人でもあごや頬骨の高さ、ちょっと普通の日本人と違う気がする。
ちなみに話す言語によって性格も変わると思います。
私の話で言うと、日本語で話す時よりも英語で話すときの方が表現も開放的でフランクに話せる気がする…
英語で話す時と比べて日本語で話すときはどうしても敬語を使うので少し遠慮がちだし低姿勢になりやすいのかも。
声のトーンも変わります。
同じアジア人でも、日本人、韓国人、中国人よく似ているとは言われますが、
やはり顔立ちや話し方が少しずつ違っていて何となく区別できるのはもちろん人種の違いもありますが、やはり後天的にしゃべる言葉が違うからだと思われます。
英語を話さなくても表情筋のトレーニングで顔立ちは変えられるみたいですよ。
ストレッチをしてみたり変顔をしてみたり普段使わない顔の筋肉を動かして目覚めさせてあげると顔が引き締まるのだとか…
小さいときバービー人形みたいに鼻が高くて目鼻立ちはっきりの顔にあこがれたなぁ…
出来たら英語を話すこともトレーニングに取り入れていただきたいですけどね~😊
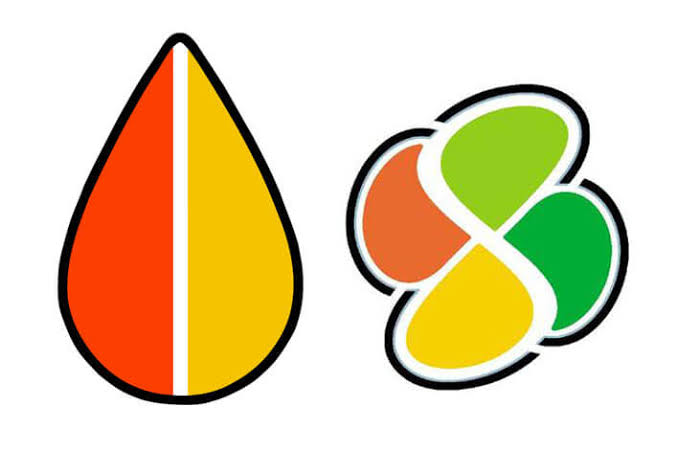
高齢者ドライバー運転卒業式
先日滋賀県大津市で起こった園児二人が死亡した事故がありましたが
高齢者ドライバーの事故が後を絶ちません
もちろん車を運転する人すべてに危険は伴うので年齢にかかわらず安全運転を心がける必要はあるのですが
全体の人口が減っているのにも関わらず、70歳以上の高齢者の起こす事故の数が減っていないことからやはり高齢になるととっさの判断力が鈍ったり、長年の無事故運転からの過信で事故を起こす確率はかなり高くなっているようです。
海外でも高齢者ドライバーの問題、年老いた両親へ運転をやめることをいつ進言するかということについての問題は日本同様深刻なようです。
これは日本の話ですが、先日テレビで見た高齢ドライバーの運転卒業式のドキュメンタリー番組。
運転能力や技術の低下、衰えにばかり目を向けずに視点を変えて、
『今まで家族のために運転をしてくれてありがとう。お父さんお疲れさまでした。』
と、これまでの運転人生を振り返るような写真スライドを作成して子ども、孫などみんなで免許返納式?をお祝いすることを儀式的にやってしまう。という試み。
本人に自主返納させるようにうまく話すことができたとしても、公共交通機関の発達していない地域では事実上生活圏内から出る交通手段をなくすこととなり、行動範囲が狭くなることによって引きこもりやうつ病を引き起こすこともあるというような意見も。
『高齢ドライバーは経験も豊富で自信と思いやりもある。』と肯定したうえで運転能力の検査や安全運転のための講習も行われています。それでも早期に限界に気付いてもらい、免許返納した方には運転以外の楽しみを見つけ、心身ともに健康で過ごせるようにするような取り組みが今後は必要になるでしょうね。
ちなみに写真の高齢者ドライバー用もみじマーク。
2011年にデザインが変更になりましたが、どちらのマークも使用可能。
表示していなくても罰則にはなりませんが、免許の交付を受けてから一年未満のドライバー対象の初心者マーク🔰(若葉マーク)は表示していないと道路交通法違反で罰金4000円。行政処分点数は1点の減点となりますので要注意です。

在日外国人が好きな日本食
職業柄、ALTや保育園、塾などで指導する外国人講師と話すことが結構あるのですが、
よく話題に上がるのは食べ物の話。
英語圏でも、国が違えば食文化が変わるので一概にはいえないのですが、やっぱり日本食は人気!
ジャンキーな食べ物が大好きだったあるイギリス人の先生。
煮物は最初味が薄くて物足りなかったと感じていたけれど
今では素材の甘みとちゃんとお出汁を引いて作った日本食の奥深さを堪能しているとの事(笑)
よく耳にする好きな日本食はやっぱり
天ぷら、寿司、ラーメン
でも毎日家庭料理を作るALTに聞いたら意外な答えが返ってきました。
焼きそばと鍋焼きうどん、そうめん。
ありますよね、ソース付きのあれですよ。
野菜と肉と炒めて粉末スープをかけたらはい出来上がり!!
鍋焼きうどんに関してはアルミに入ったうどんと具材を火にかけるだけで食べられるんですから。納得。
たこ焼きは中に入っているタコが賛否両論。
特定の国では”devil fish”と呼ばれて絶対に食べない人もいれば、食べてみたら意外とおいしかったという人も。
子どもがくるくる回して自分で作るのが楽しくて好きだということから中にウインナーや肉、チーズなどを入れて食べたりするそうです。
先日アップル社の設立者のスティーブ=ジョブズについての記事を読んだのですが
親日家だったジョブズはベジタリアンだったようですが、お寿司と蕎麦が大好物だったそうです。
シェフを築地で修業させて刺身の乗った蕎麦をアップル社の食堂のメニューとして作らせていたというびっくりエピソードも。
香り高く、ヘルシーな日本食。
海外でも在日外国人にも愛されるのは日本人として誇らしいなと感じる今日この頃。
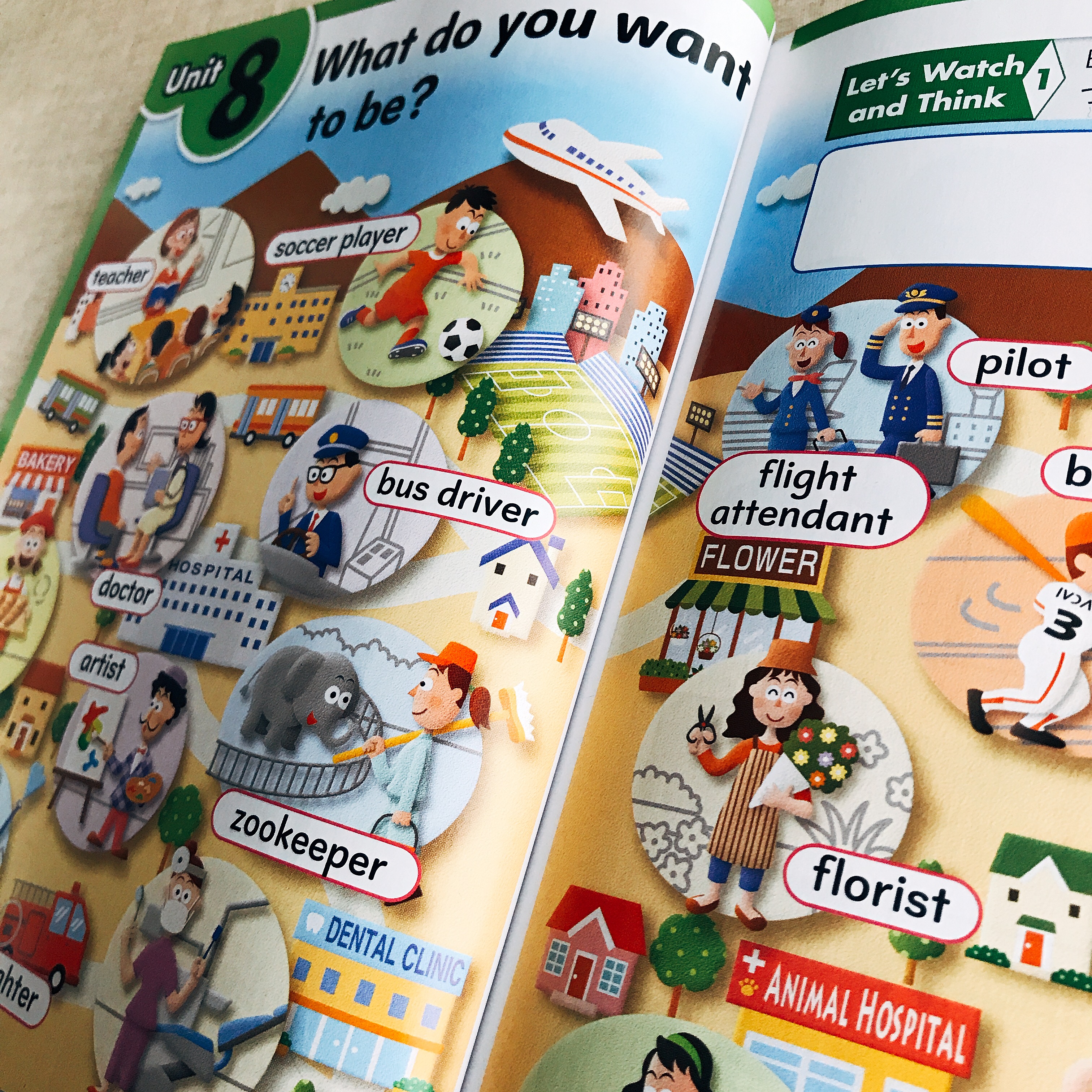
小学校英語 2020年の教育改革に向けて
LAC英会話教室講師は
お昼間は小学校で英会話の補助教員をしています。
自宅教室は少人数制でやっていますが(マンツーマンのクラスもあります)
学校では30人から40人くらいの子供たちを英語専門の先生、もしくは担任の先生と出来るだけオールイングリッシュで進めています。
→私は英語でしか喋らない先生だと子どもたちも認識しているので拙いながらも一生懸命にブロークンイングリッシュで話しかけてくれるところがかわいい😍
絵や手紙をプレゼントしてくれたり、サインをくださいってノートを持ってきたり…
ぐんぐん水を吸うオアシスのように柔軟な思考と、レコーダーのような耳と記憶力の小学生時代に英語に触れ合えるのは素敵なことだといつも思います。
1、2年生もALTの先生が各学期に1回ずつ来て英語に触れる機会はありますが、
3年生からは本格的に外国語が教科として時間割に組み込まれています。
学校によって進度や学習指導案は異なるのですが、3年生は
『How many…?』
という数の数え方から始まり、6年生の終わりには
『What do you want to be?』
自分の将来の夢について英語で考え、友達の前でプレゼンテーションするということを目標に進めていきます。
教室での気づきや指導方法を学校で活かし
学校で子供たちに興味を持ってもらえたゲームや教材を教室でも実践する。
という相互作用が働いてより楽しく学べるようにとあの手この手でレッスンを実施しています✨
より多くの子供たちが楽しく、興味をもって語学を習得できるように日々研究中✏️
英語だけでなく日本語でのコミュニケーションも大切に…
今現在運動会やスポーツフェスティバルの練習で暑い中外で長時間過ごすことの多い子ども達。
まだまだ体が暑さに慣れていないので体調を崩しやすい時期だと思います。
水分と睡眠をしっかりとって乗り切りましょうね♪

ランドセル購入活動-ラン活-
ゴールデンウィーク中、さぞかしショッピングモールは人が多いのだろうな…
と思いながら出かけたのですが、意外と人が少なくて拍子抜けしてしまいました。
そんな中でも売り場がにぎわっていたのは…
ランドセル売り場。
以前にもちらっとお話しましたが、9年前長女が新一年生になる時には秋に購入して
入学直前の受け取りでした。
今日はランドセル売り場、来年一年生になるお子さんとそのご両親やおじいちゃんおばあちゃんなどが一緒にランドセルを選ぶ光景が…
最近では、ゴールデンウィークにはいろんなお店に足を運び、ある程度候補を絞って6月中には購入という方がほとんどのようです。
今年の新一年生を見ていて思ったのは、やはり男の子はシンプルに黒が一番多く、続いて紺や青。それ以外の色はほとんど目にしないように思います。
女の子は定番カラーの赤、ピンクに続きブラウンや水色、メタリックの紫などをよく見かけます。
キャメルブラウンはあの『花より男子』の続編?『花のち晴れ』に出てくる英徳学園初等部のランドセルの影響?
最近よく見るようになりました。
6年間使うものだから、機能的で飽きの来ない色とデザインなど選ぶ要素はたくさんあるのですが、
本人の本当に気に入ったものを購入して大切にしてもらうか、あまりにも奇抜な色をチョイスした時にはある程度誘導して違う色を購入するように仕向ける?かというような攻防が本日も繰り広げられていました。
そんな中、ネット広告で見かけた高島屋は篠原ともえさんデザインのランドセル。
繊細な和の刺繍が施されたランドセルは78,000円+taxとお値段は少々高めですが、とっても上品でかわいらしいデザイン。
いろんなランドセルがあるんですね~。
少子化に加え、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん×2の6ポケットで一人一人にかける費用は上がってきているように思います。かわいい孫子が6年生まで使うお守りのようなランドセル。なおさら選ぶのにも力が入りますよね…。
写真のランドセルは
ロデオのヒストリア。
なんだかとってもおしゃれ✨
いかにもお勉強ができそうな子にみえますね。
ちなみに再度ランドセル豆知識
『ランドセル』はオランダ語から作られた和製語。
英語ではないので通じないのですが
“Book bag.”
“School bag.”
と呼びます。ちなみに前に”Japanese”をつけると、日本のランドセルとして理解されやすいかと。
海外では日本のランドセル、丈夫で大容量なことから大人のオシャレアイテムとして人気なのですよ♪
